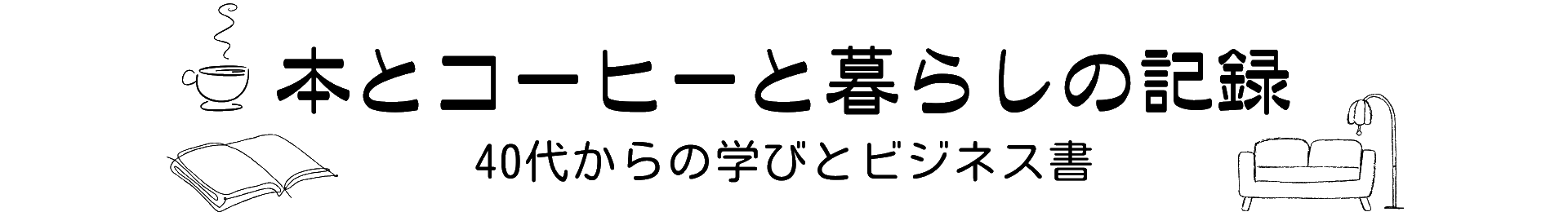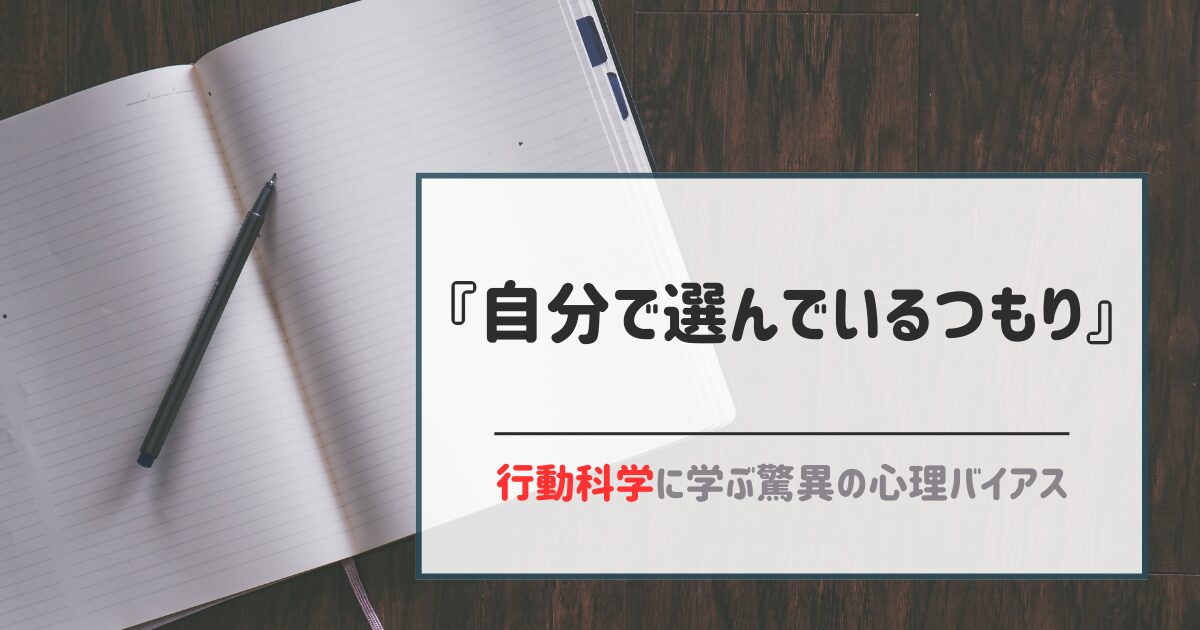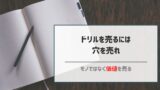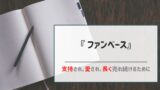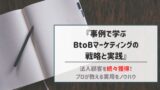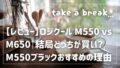一番楽しかったこと、一番楽しくなかったこと、一番最後の瞬間が人の記憶に残りやすい。
「なぜ、私たちは【選んでいるつもり】になってしまうのか?」
日々の買い物や選択、実はその多くが無意識のうちに誘導されています。
本記事では、行動科学の知見をもとに、「人の行動を変える仕組み」をわかりやすく要約。
マーケティング担当者、営業職、商品企画など「人を動かす仕事」に携わる方にとって、すぐに使える実践的なヒントが満載です。
「なぜあの商品が売れるのか?」
「なぜあの人の話は聞きたくなるのか?」
本書は、私たちが無意識のうちに行動を決定する心理のカラクリを、豊富な研究事例とともに解き明かしてくれる一冊です 。
ビジネスや人間関係、さらには自分自身の習慣づくりにも役立つ実践的な知識が身につきます 。
読書が苦手な学生さんや社会人の方、経営に関わる方にも、読みやすくコンパクトに要約しています。ビジネス書や自己啓発の本、まずは要点だけでも読んでみませんか。
『自分で選んでいるつもり』
行動科学に学ぶ驚異の心理バイアス
著者 : リチャード・ショットン
翻訳 : 上原 裕美子 (翻訳)
発売日: 2024年5月
出版社: 東洋経済新報社
ページ: 306ページ
【こんな人におすすめ】行動科学で解決できる5つの悩み
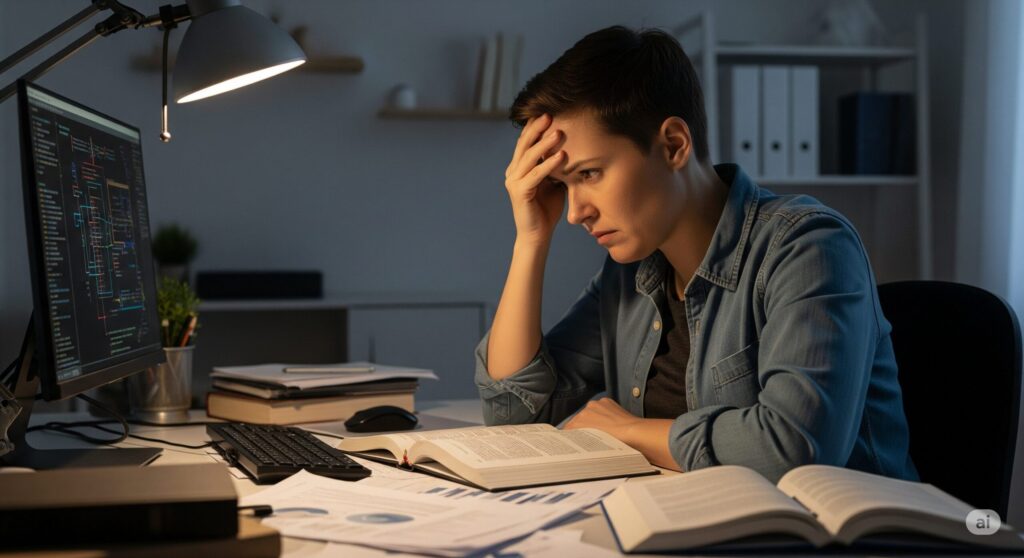
マーケティングやセールスに携わる人
消費者の購買意欲を高めるための具体的な心理テクニックや、商品の魅力を効果的に伝える方法が学べます。
単なる感覚に頼るのではなく、科学的根拠に基づいた戦略を立てられるようになります。
新しい習慣を身につけたい人
「三日坊主」に悩むあなたも、本書の「行動を促す仕組みづくり」を応用すれば、無理なく目標を達成するヒントが見つかります。
モチベーションに頼らず、自然と行動できる環境を作る方法を学ぶことができます。
チームや部下をまとめる立場の人
強制するのではなく、相手が自ら動きたくなるようなマネジメントのコツが満載です。
言葉の使い方ひとつで、相手の行動や意識を変えることができる、円滑な人間関係を築くための知恵が得られます。
Webライティングやブログ運営に興味がある人
読者の心に響く文章、記憶に残る表現、そして行動を促す構成のヒントが得られます。
単に情報を伝えるだけでなく、読者を巻き込む力強いコンテンツ作りの参考にしてください。
日々の生活や人間関係をより良くしたい人
本書に書かれている心理誘導の知識は、身近な人間関係にも応用できます。
相手の気持ちを理解し、より良いコミュニケーションを築くための視点を提供してくれます。
【10の学び】人を動かすための行動科学の要点

習慣形成のタイミングと仕組み化
人は新しい期間が始まるタイミング(週の始め、月の始め、誕生日など)に、新しい行動を受け入れやすいという傾向があります。
行動を促すには、モチベーションだけに頼るのではなく、既存の習慣と新しい行動を結びつける「習慣の積み上げ(ハビットスタッキング)」といった、具体的なキュー(手がかり)を作ることが重要です。
「簡単にする」ことの重要性
人が行動を起こさない理由を探り、その障壁となる「摩擦」を取り除くことが重要です。
まずは手間が最小限の「ささやかな行動」を頼むことで、相手の自己認識に変化を与え、その後の本当の目的を達成しやすくします。
あえて「面倒にする」という逆の発想
行動科学の興味深い点として、「簡単にする」の真逆である「面倒にする」ことが効果的な場面もあります。
たとえば、商品に少し手間をかけさせることで、人はその対象に価値を感じる「イケア効果」などが挙げられます。
これは、消費者の行動を変えるよりも、品質に対する評価を高めたい場合に適した方法です。
相手の思考を促す「産出効果」
優れた広告や文章は、受け手に少しだけ頭を使わせることで記憶に残りやすくなります。
例えば、「なるほど、そういうことか」と納得させるような謎や、問いかけの形式を用いることで、読み手は主体的に考え、その内容を受け入れやすくなります。
音や文字がもたらす「キーツ・ヒューリスティック」
韻を踏んだ文章や発音しやすい言葉は、処理しやすく、真実味が増して感じられます。
この「キーツ・ヒューリスティック」は、消費者に安心感を与えたい場合に役立ちます。
逆に、発音しにくい名前は、スリルやリスクを強調したい場合に効果的です。
具体的な言葉で心に刻む
抽象的な表現ではなく、「ポケットに1000曲」のように具体的な言葉を使うことで、メッセージは記憶に残りやすくなります。
また、シンプルな言葉は、コミュニケーションがうまいという証拠にもなり、信頼感を高めます。
専門家ほど抽象的な言葉を使いがちですが、消費者は具体的な言葉に惹かれます。
「キリの悪い数字」がもたらす信頼感
ハインツのケチャップ「57種類」のように、キリのいい数字よりも、細かい数字を使うことで正確さや信憑性が高く評価される傾向があります。
人は「細かい部分まで言えるなら正確なはず」と無意識に判断するため、価格や数量でこのテクニックを使うと効果的です。
極端を避ける心理「極端回避」
人は3つの選択肢を提示された場合、真ん中のものを選びやすいという傾向があります。
これを「極端回避」と呼びます。
この心理を利用して、本当に売りたい商品を真ん中の価格帯に配置したり、超高級な「おとり商品」を提示することで、消費者の選択を誘導することができます。
損失を強調する「フレーミング効果」
同じ内容でも、表現方法(フレーミング)を変えるだけで受け手の印象は大きく変わります。
特に「得をする」ことよりも「損をする」ことに人は強く反応します。
また、「完売」と「取扱不可」の表示のように、言葉の選択ひとつで商品の人気ぶりを伝え、顧客の不満を軽減することも可能です。
公正さと自由の尊重
人はたとえ自分が損をしても、不公正な相手を罰する傾向があります。
この「公正さ」を求める心理を利用し、価格設定などに配慮することで、消費者の信頼を得ることができます。
また、強制的なメッセージは反発を招くため、「選択はあなたの自由です」と伝えることで、相手の行動を促す効果があります。
【まとめ】自分で選んでいるつもり|行動科学で人生を変える心理テクニック

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
内容についていかがでしたでしょうか。
書籍『自分で選んでいるつもり』を読み解き、行動科学に基づいたマネジメントや心理誘導の要点をまとめました。
- 習慣化はタイミングと仕組みづくりが鍵
- 行動を促すには、まず「摩擦」を取り除き、簡単にすることから始める
- あえて手間をかけることで、物の価値を高める効果も
- 「なるほど」と思わせる問いかけは、読者を巻き込む力がある
- 具体的でシンプルな言葉は、記憶に残りやすく、信頼感を生む
- 価格や数字は、キリの悪い数字を使うことで正確さをアピールできる
- 消費者の選択を誘導したいなら、真ん中の選択肢や「おとり」を利用する
- 同じ内容でも、損失を強調したり、名詞を使ったりすることで説得力が増す
- 相手の自由を尊重する姿勢が、かえって行動を促すことがある
これらの知識は、私たちが日々の生活で無意識のうちに経験している心理現象の裏側を教えてくれます。
読みながら何度も「これ、自分にも当てはまってる…」とドキッとしました。
選んでいるつもりで、実は選ばされていたなんて。
しかも、その仕掛けがちゃんと科学で裏付けされてるという事実がまたおもしろい。
「なぜか選ばれている」「気づけば買っていた」…
そんな【選択】の裏側を知ることで、きっとあなた自身の発信や提案の仕方も、ちょっと変わってくるはずです。
マーケティングをやっている人はもちろん、普段はあまり本を読まない人にもぜひおすすめしたい一冊でした。
この記事を読んでくださったあなたが、どんな立場にあっても、何かひとつでも「これやってみようかな」と思えるヒントを見つけてくれていたら、うれしいです。
みなさんも「行動科学」を応用してみてはいかがでしょうか。
マーケティングについて、以下の書籍『ドリルを売るには穴を売れ』、『ファンベース』『事例で学ぶ BtoBマーケティングの戦略と実践』についても、要約にしています。
興味のある方はこれらの記事もご覧ください。
引用箇所において一部誤入力があるかもございません。予めご了承下さい。