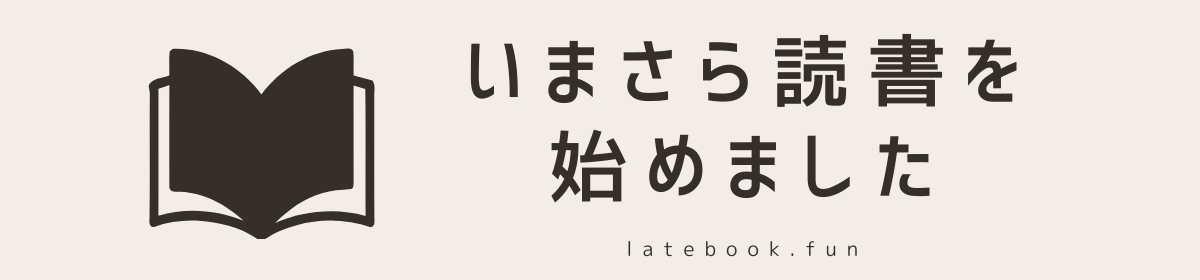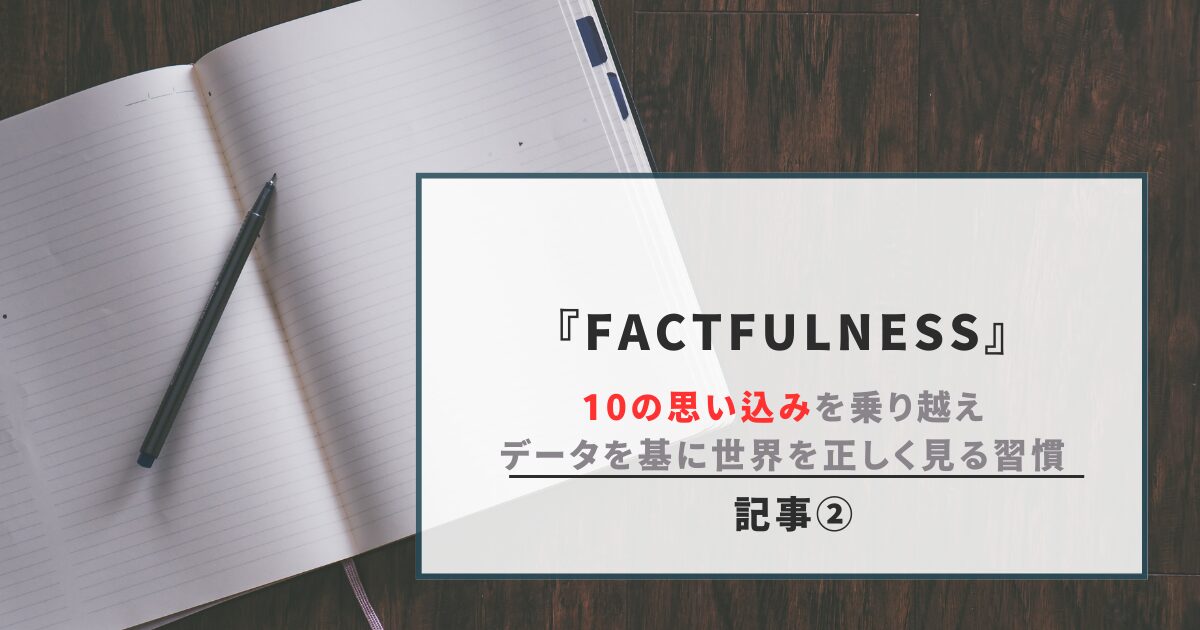誰もが持っているであろう「思い込み」。それはどれだけ正しい事実か。改めて正しい事実をみるためには何が必要か、「ファクトフルネス」とは?についての書籍となります。私が読んでいるときに、マーキングした文章の一部を2回に分けて記載します。今回はその2回目の記事となります。
プロフィールにも書いていますが、もともと読書が苦手な私が、この本を読んで印象に残ったことをまとめてみました。個人的な感想ですが、よかったら参考にしてみてください。
📘 『FACTFULNESS』
10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣
著者 : ハンス・ロスリング、オーラ・ロスリング、アンナ・ロスリング・ロンランド
翻訳 : 上杉 周作、関 美和
発売日: 2019年1月
出版社: 日経BP
ページ: 400ページ
🔰こんな方にオススメ
情報があふれる今の時代、「何を信じたらいいかわからない」と感じている人、あるいはSNSやニュースに振り回されがちな人にとって、自分の考え方を見直すきっかけにもなる本です。また、先入観にとらわれがちな人や、つい感情で判断してしまうことが多い人にも、新しい視点をくれる一冊です。読んだ後は、世界の見え方が少し前向きになるかもしれません。
📍ピン留めしておきたいこと『5選』
「〇〇人だから~」みたいな決めつけ
同じ集団の中にある違いを探そう。集団が大規模な場合は特に、より小さく、正確な分類に分けたほうがいい。
違う集団のあいだの共通項を探そう。異なる集団のあいだに、はっとするような共通点を見つけたら、分類自体が正しいかどうかを改めて問い直そう。
違う集団のあいだの違いも探そう。ひとつの集団(たとえば、レベル4の生活を送る人、意識のない兵士)について言えることが、別の集団(レベル4でない生活を送る人、眠っている赤ちゃん)にも当てはまると思い込んではいけない。
「過半数」に気をつけよう。過半数とは半分より多いということでしかない。それが51%なのか、99%なのか、そのあいだのどこなのかを確かめたほうがいい。
強烈なイメージに注意しよう。強烈なイメージは頭に残りやすいが、それは例外かもしれないと疑ったほうがいい。
自分以外はアホだと決めつけないようにしよう。変だと思うことがあったら、好奇心を持ち、謙虚になって考えてみよう。それはもしかしたら賢いやり方なのか、だとしたらなぜ賢いやり方なのか、と自問しよう。
グループにラベルを貼って、それで全部わかった気になることもゼロではないことを反省、、、。実際は一人ひとり違うし、似てるようで全然違う部分もある。もっとフラットに人を見るべきだと思いました。
「変わらない」は思い込みだった
小さな進歩を追いかけよう。毎年少しずつ変化していれば、数十年で大きな変化が生まれる。
知識をアップデートしよう。賞味期限がすぐに切れる知識もある。テクノロジー、国、社会、文化、宗教は刻々と変わり続けている。
おじいさんやおばあさんに話を聞こう。価値観がどれほど変わるかを改めて確認したかったら、自分のおじいさんやおばあさんの価値観がいまの自分たちとどんなに違っているかを考えるといい。
文化が変わった例を集めよう。いまの文化は昔から変わらないし、これからも同じだと言われたら、逆の事例をあげてみよう。
文化とか宗教って不変に見えるけど、実は少しずつ変わっています。変化が見えにくいだけで、時代は確実に動いてるってことを実感しました。
「正解はひとつ」じゃないって肝に銘じたい
自分の考え方を検証しよう。あなたが肩入れしている考え方が正しいことを示す例ばかりを集めてはいけない。あなたと意見の合わない人に考え方を検証してもらい、自分の弱点を見つけよう。
知ったかぶりはやめよう。自分の専門分野以外のことを、知った気にならないほうがいい。知らないことがあると謙虚に認めよう。その道のプロも、専門分野以外のことは案外知らないものだ。
めったやたらとトンカチを振り回すのはやめよう。何かひとつの道具が器用に使える人は、それを何度でも使いたくなるものだ。ひとつの問題を深く掘り下げると、その問題が必要以上に重要に思えたり、自分の解がいいものに思えたりすることがある。でも、ひとつの道具がすべてに使えるわけではない。あなたのやり方がトンカチだとしたら、ねじ回しやレンチや巻き尺を持った人を探すといい。違う分野の人たちの意見に心を開いてほしい。
数字は大切だが、数字だけに頼ってはいけない。数字を見なければ世界を知ることはできないが、数字だけでは世界を理解できない。数字が人々の生活について何を教えてくれるかを読み取ろう。
単純なものの見方と単純な答えには警戒しよう。歴史を振り返ると、単純な理想論で残虐な行為を正当化した独裁者の例にはことかかない。複雑さを喜んで受け入れよう。違う考え方を組み合わせよう。妥協もいとわないでほしい。ケースバイケースで問題に取り組もう。
問題を見たとき、つい「答えはこれだ」って決めつけることはあるが、実際は複雑でケースバイケース。単純な答えほど危ういっていうのが深く刺さりました。
誰かを責めても何も変わらない
犯人ではなく、原因を探そう。物事がうまく行かないときに、責めるべき人やグループを捜してはいけない。誰かがわざと仕掛けなくても、悪いことは起きる。その状況を生み出した、絡み合った複数の原因やシステムを理解することに力を注ぐべきだ。
ヒーローではなく、社会を機能させている仕組みに目をむけよう。物事がうまくいったのは自分のおかげだと言う人がいたら、その人が何もしなくても、いずれ同じことになっていたかどうかを考えてみるといい。社会の仕組みを支える人たちの功績をもっと認めよう。
問題が起きたときに、犯人を探すんじゃなくて「何がそうさせたか?」に目を向ける姿勢。これは仕事でも人間関係でも、すごく大事だなと感じました。
焦らず、一歩ずつでも
深呼吸しよう。焦り本能が顔を出すと、ほかの本能も引き出されて冷静に分析できなくなる。そんな時には時間をかけて、情報をもっと手に入れよう。いまやらなければ二度とできないなんてことはめったにないし、答えは二者択一ではない。
データにこだわろう。緊急で重要なことならなおさら、データを見るべきだ。一見重要そうだが正確でないデータや、正確であっても重要でないデータには注意しよう。正確で重要なデータだけを取り入れよう。
占い師に気をつけよう。未来についての予測は不確かなものだ。不確かであることを認めない予測は疑ったほうがいい。予測には幅があることを心に留め、決して最高のシナリオと最悪のシナリオだけではないことを覚えておこう。極端な予測がこれまでどのくらい当たっていたかを考えよう。
過澈な対策に注意しよう。大胆な対策を取ったらどんな副作用があるかを考えてほしい。その対策の効果が本当に証明されているかに気をつけよう。地道に一歩一歩進みながら、効果を測定したほうがいい。ドラマチックな対策よりも、たいていは地道な一歩に効果がある。
「今すぐ決めなきゃ!」って焦ると視野が狭くなる。冷静に情報を集めて、一歩ずつ進めばいいっていうメッセージにすごく救われた気がしました。
💡まとめ
つい人を「○○な人」と決めつけてしまいがちだけど、実は一人ひとり違う。文化や価値観も、変わらないように見えて少しずつ変化しているし、問題にはいつも単純な正解があるわけじゃない。誰かを責めるよりも、なぜそうなったかを考える視点も大切。焦ったときほど深呼吸して、地道に一歩ずつ進むほうがいい。そんな、見方や考え方を少し広げてくれる内容がつまった一冊でした。
最後に。
謙虚であるということは、本能を抑えて事実を正しくみることがどれほど難しいかに気づくことだ。
好奇心があるということは、新しい情報を積極的に探し、受け入れるということだ。自分の考えに合わない事実を大切にし、その裏にある意味を理解しようと努めることだ。
前の記事「FACTFULNESS①」はこちらになります。
引用箇所において一部誤入力があるかもございません。予めご了承下さい。