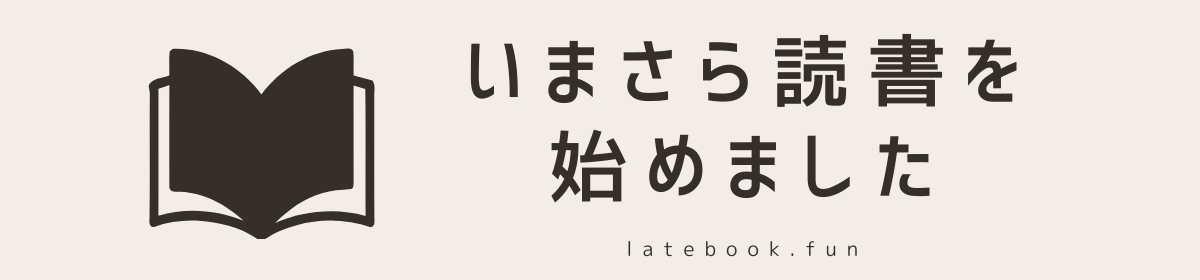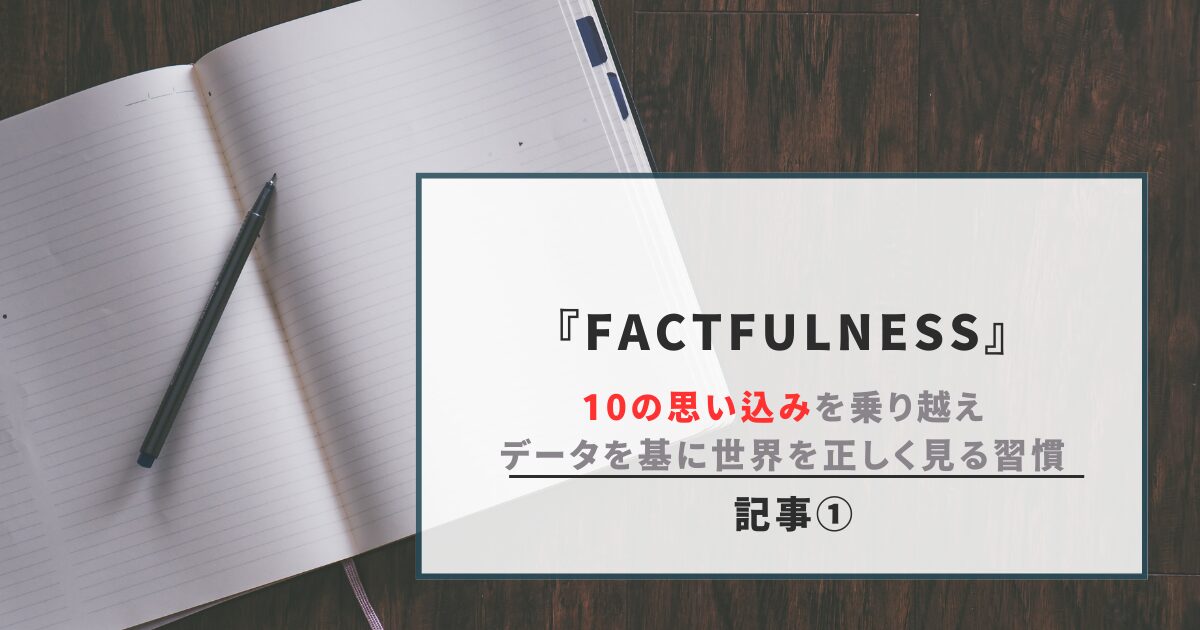誰もが持っているであろう「思い込み」。それはどれだけ正しい事実か。改めて正しい事実をみるためには何が必要か、「ファクトフルネス」とは?についての書籍となります。私が読んでいるときに、マーキングした文章の一部を2回に分けて記載します。今回はその1回目の記事となります。
プロフィールにも書いていますが、もともと読書が苦手な私が、この本を読んで印象に残ったことをまとめてみました。個人的な感想ですが、よかったら参考にしてみてください。
📘 『FACTFULNESS』
10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣
著者 : ハンス・ロスリング、オーラ・ロスリング、アンナ・ロスリング・ロンランド
翻訳 : 上杉 周作、関 美和
発売日: 2019年1月
出版社: 日経BP
ページ: 400ページ
🔰こんな方にオススメ
情報があふれる今の時代、「何を信じたらいいかわからない」と感じている人、あるいはSNSやニュースに振り回されがちな人にとって、自分の考え方を見直すきっかけにもなる本です。また、先入観にとらわれがちな人や、つい感情で判断してしまうことが多い人にも、新しい視点をくれる一冊です。読んだ後は、世界の見え方が少し前向きになるかもしれません。
📍ピン留めしておきたいこと『5選』
「二極化してる」って思い込みだったかも
「平均の比較」に注意しよう。分布を調べてみると、2つのグループに重なりがあり、分断などないことが多い。
「極端な数字の比較」に注意しよう。人や国のグループには必ず、最上位層と最下位層が存在する。2つの差が残酷なほど不公平なときもある。しかし多くの場合、大半の人や国はその中間の、上でも下でもないところにいる。
「上からの景色」であることを思い出そう。高いところから低いところを正確に見るのは難しい。どれも同じくらい低く見えるけれど、実際は違う。
国や人を「貧しい/豊か」「発展途上/先進国」みたいに分けて考えがちですが、実際はその中間にいる人が大多数であることに気づかされました。もっと全体の分布を見る目が必要と感じました。
悪いニュースばかりに引っ張られてたかも
「悪い」と「良くなっている」は両立する。「悪い」は現在の状態、「良くなっている」は変化の方向。2つを見分けられるようにしよう。「悪い」と「良くなっている」が両立し得ることを理解しよう。
良い出来事はニュースになりにくい。ほとんどの良い出来事は報道されないので、ほとんどのニュースは悪いニュースになる。悪いニュースを見たときは、「同じくらい良い出来事があったとしたら、自分のもとに届くだろうか?」と考えてみよう。
ゆっくりとした進歩はニュースになりにくい。長期的には進歩が見られても、短期的に何度か後退するようであれば、その後退のほうが人々に気づかれやすい。
悪いニュースが増えても、悪い出来事が増えたとは限らない。悪いニュースが増えた理由は、世界が悪くなったからではなく、監視の目がより届くようになったからかもしれない。
美化された過去に気をつけよう。人々は過去を美化したがり、国家は歴史を美化したがる。
ニュースを見てると「世界ってどんどん悪くなってる…」と感じてしまうことが多いですが、良いことは報道されづらいだけです。少しずつでも前に進んでるって視点がとても大事だと思いました。
グラフはいつも直線ではない
なんでもかんでも、直線のグラフを当てはめないようにしよう。多くのデータは直線ではなく、S字カーブ、すべり台の形、コブの形、あるいは倍増する線のほうが当てはまる。子供は、生まれてから半年で大きく成長する。でも、いずれ成長がゆっくりになることは、誰にだってわかる。
「このままいくと大変なことに…」みたいな話にはつい引っ張られがちだけど、成長や変化って必ずしも一直線ではなく、もっと柔軟に未来をイメージしないといけないと思いました。
「怖い=危ない」ではないということに納得
世界は恐ろしいと思う前に、現実を見よう。世界は、実際より恐ろしく見える。メディアや自身の関心フィルターのせいで、あなたのもとには恐ろしい情報ばかりが届いているからだ。
リスクは、「危険度」と「頻度」、言い換えると「質」と「量」の掛け算で決まる。リスク=危険度x頻度だ。ということはつまり、「恐ろしさ」はリスクとは関係ない。
行動する前に落ち着こう。恐怖でパニックになると、物事を正しく見られなくなる。パニックが収まるまで、大事な決断をするのは避けよう。
感情と事実を分けて考えることはとても難しいけど大切。怖さに反応するのではなく、冷静にリスクを計算するクセをつけていきたいと思いました。
数字を鵜呑みにしない癖をつける
比較しよう。大きな数字は、そのままだと大きく見える。ひとつしかない数字は間違いのもと。必ず疑ってかかるべきだ。ほかの数字と比較し、できれば割り算をすること。
80・20ルールを使おう。項目が並んでいたら、まずは最も大きな項目だけに注目しよう。多くの場合、小さな項目は無視しても差し支えない。
割り算をしよう。割合を見ると、量を見た場合とはまったく違う結論にたどり着くことがある。たいていの場合、割合のほうが役に立つ。特に、違う大きさのグループを比べるのであればなおさらだ。国や地域を比較するときは、「ひとりあたり」に注目しよう。
大きな数字に圧倒されるますが、比較や割合を使うだけでまったく違う見え方になります。データを見る力を磨くことができると、多角的にものを見ることができると感じました。
パレートの法則 (80 対 20 の法則) というものとがあり、20% の要因からおよそ 80% の結果が生まれるという現象を表す用語となります。
💡まとめ
ニュースや数字を見て「世界はどんどん悪くなってる」と感じることもあるけれど、実は少しずつ良くなっていることもたくさんあります。物ごとを「良い・悪い」や「豊か・貧しい」と単純に分けず、その間にいる多くの人やゆっくり進む変化に目を向けることが大切。怖いと感じる情報も、冷静にリスクを考えれば見え方が変わります。数字やグラフも正しく読み取ることで、もっと本当のことが見えてくるかもしれません。
「ネガティブ本能」の「良い出来事はニュースになりにくい」、「美化された過去に気をつけよう。人々は過去を美化したがり、国家は歴史を美化したがる。」については、ネックになってしまう本能だと感じました。
次の記事「FACTFULNESS②」はこちらになります。
引用箇所において一部誤入力があるかもございません。予めご了承下さい。