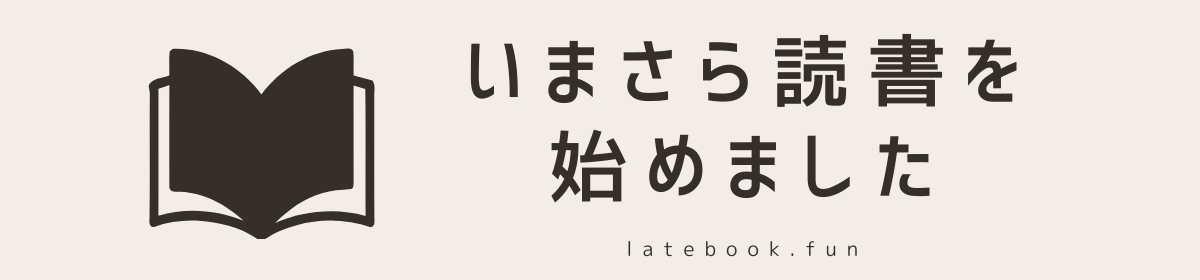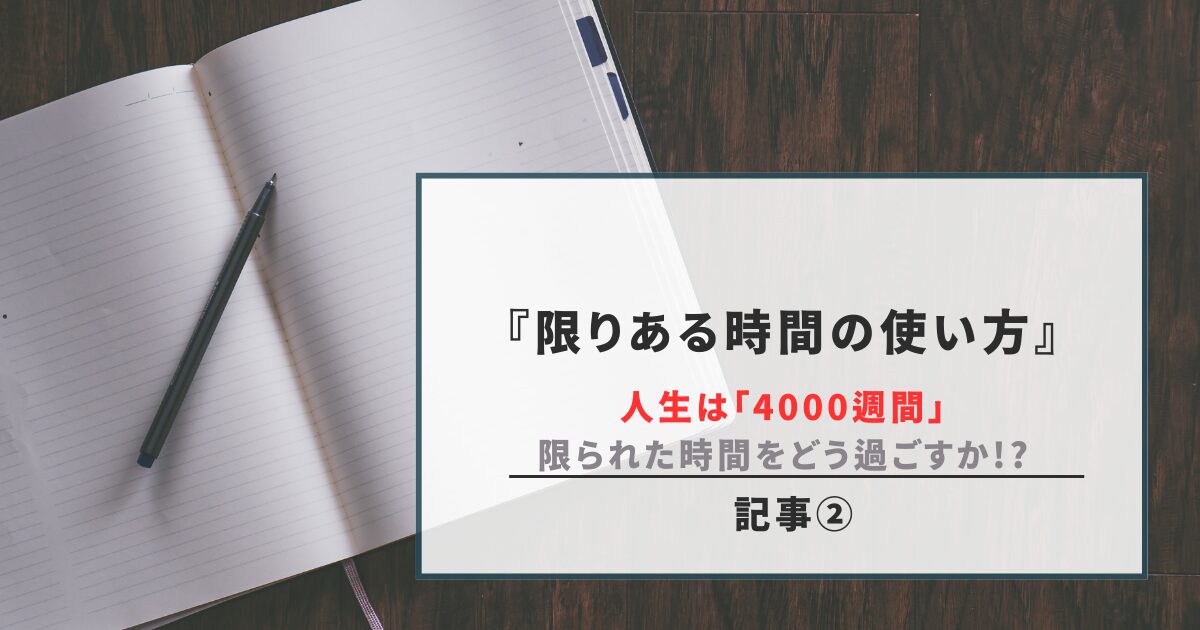80歳まで生きるとして、自分の限られた4000週間をいかに過ごすか?ついての書籍となります。私が読んでいるときに、マーキングした文章の一部を2回に分けて記載します。今回はその2回目の記事となります。
プロフィールにも書いていますが、もともと読書が苦手な私が、この本を読んで印象に残ったことをまとめてみました。個人的な感想ですが、よかったら参考にしてみてください。
📘 『限りある時間の使い方』
人生は「4000週間」限られた時間をどう過ごすか!?
著者 : オリバー・バークマン
翻訳 : 高橋 璃子
発売日: 2022年6月
出版社: かんき出版
ページ: 304ページ
🔰こんな方にオススメ
人生と時間の有限性について深く考えさせる内容であり、「効率」や「生産性」重視の現代社会に対して疑問を投げかけながら、より人間らしく豊かな生き方について書かれています。日々時間に追われていて、どうタイムマネジメントべきか?と考えがちな人にとって、時間との関係性を考えることができると思います。
📍ピン留めしておきたいこと『5選』
まず自分の時間を確保する
時間についても同じだ。まず自分の取り分を確保しないと、どんどん他のことに時間を使ってしまい、本当に大事なことができなくなる。余った分を投資しようと思っていても、絶対に余らないのだ。
本当にやりたいことがあるなら(創作活動でも、恋愛でも、社会運動でも)、確実にそれをやり遂げるための唯一の方法は、今すぐに、それを実行することだ。どんなに石が小さく見えても、どんなに他の大きな石があっても、そんなのは関係ない。
今やらなければ、時間はないのだ。
「時間が余ったらやろう」は通用しません。まず最初に、自分が本当にやりたいことのための時間を押さえる。そうしないと、時間は他人や雑事に奪われます。
「非目標性の時間」が人生を潤す
哲学者のキーラン・セティヤはこういう活動を「非目標性の活動」と呼ぶ。好きな曲を聴いたり、友人と会って話したりするとき、僕たちは何らかの目標に向かっているわけではない。その価値は目標達成ではなく、ただその活動をすることにある。
何らかの達成を目標とするのではなく、ただ活動そのものを楽しむこと。僕たちはそんな活動をもっと日々の生活に取り入れたほうがいい。
目的のない活動―音楽を聴いたり、ただ散歩したり、友達と笑い合ったり。
それ自体に意味がある時間こそが、僕たちを人間らしくしてくれます。
便利さに流されすぎると、自分を見失う
便利であるとは、要するに手軽なことだ。でも手軽なことがつねに最善であるとはかぎらない。
便利さばかりを優先していると、自分が何をやりたいのかわからなくなる。
手間を省くばかりを考えると、何がしたいのか分からなくなる。不便で、手のかかることの中に、人生の豊かさは宿ります。
「選ぶこと」は「失うこと」でもある
何かに時間を使うと決めたとき、僕たちはその他のあらゆる可能性を犠牲にしている。その時間にできたはずのことは山ほどあるけれど、それでも僕たちは、断固として、やるべきことを選ぶのだ。
何かを選ぶということは、その他すべての可能性を捨てること。
でもその決断こそが、選びとったものに価値を与え、心に満足をもたらします。
「何のためでもない時間」を持とう
何の役にも立たないことに時間を使い、その体験を純粋に楽しむこと。将来に備えて自分を高めるのではなく、ただ何もしないで休みこと。
一度きりの人生を存分に生きるためには、将来に向けた学びや鍛錬をいったん忘れる時間が必要だ。怠けることは単に許容されるだけでなく、人としての責任だといっていい。
人生は準備期間ではありません。
何の成果にもつながらない「無益な時間」こそが、真に心を解放してくれます。
怠けることは「人としての責任」とさえ言えるかもしれません。
✏️その他書き留めておきたいこと
効率を上げれば上げるほど、ますます忙しくなる。タスクをすばやく片付ければ片付けるほど、ますます多くのタスクが積み上がる。
本当はなかったかもしれない貴重な時間の過ごし方を、自分自身で選びとった結果なのだから。
知っている人も多いと思うけれど、僕たちが利用している「無料」のソーシャルメディアは、実は無料ではない。そこであなたは顧客ではなく、商品だからだ。
今を生きるとは、今ここから逃れられないという事実を、ただ静かに受け入れることなのかもしれない。
「わからないという不快感に耐えれば、解決策が見えてくる」
「すべての問題を解決済みにする」という達成不可能な目標を諦めよう。
初期の試行錯誤の段階で諦めてしまうようでは、けっしてオリジナル作品はつくれない。
たとえ一流のシェフになれなくても、子どもたちに栄養バランスのいい食事を用意することは、何にも代えがたい重要な行為だ。
時間を支配しようとする態度こそ、僕たちが時間に苦しめられる原因である。
💡まとめ
どれも心に響く内容でしたが、特に「非効率な時間こそが豊かさを育む」という視点は、これまでの自分にはなかった考え方でした。これまでは「無駄なく過ごすこと=良い時間の使い方」だと思い込んでいたけれど、実はその“余白”の中にこそ、自分らしさや豊かさが息づいていたのかもしれません。
完璧さを求めてしまいがちな自分にとって、「不完全さを受け入れる」というメッセージもとても救いになりました。人生はきっと、うまくいかないことの連続。それを否定するのではなく、ただ「そういうものだ」と受け止めるだけで、気持ちはずっと軽くなる気がします。
そして、日々の情報の波に流されっぱなしの生活の中で、「SNSやスマホから少し離れてみる」「今ここに意識を向ける」という習慣が、自分を整えるカギになることにも気づかされました。
時間は限られている。でもだからこそ、そこに価値があるんですよね。これからは、ただ忙しく過ごすのではなく、“限られた時間をどう生きるか”を大切にしていきたいと思います。
前の記事「限りある時間の使い方①」はこちらになります。
引用箇所において一部誤入力があるかもございません。予めご了承下さい。