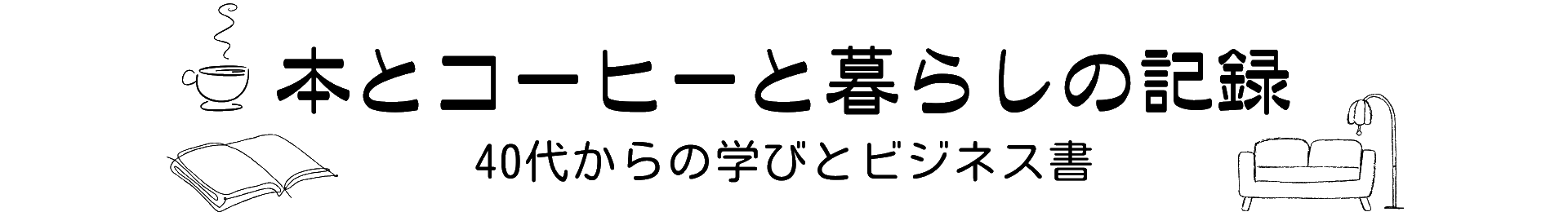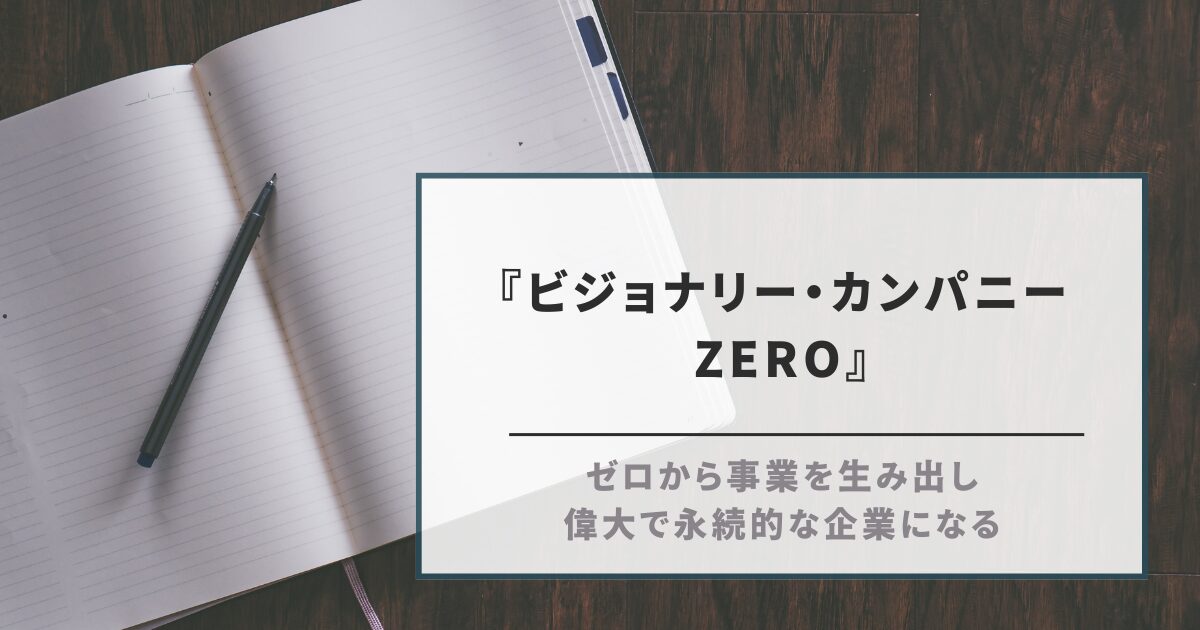戦略や仕組みよりもまず、人と文化が大切。誰を仲間にするのか、どんな価値観を共有するのか。
まだまだ「本」というものに抵抗がある時期で、書籍に関して右も左もわからない時。会社の人から渡された一冊。
私の第一印象は「分厚っ、、、」
とはいえ、ちゃんと読まなければいけない空気感があったので、読むことを決意。
読み始める前に、まずはタイトルの「ZERO」というワードが気になったので調べてみました。
すると、以下のようにシリーズものになっていることを知りました。
著者はジム・コリンズ(Jim Collins)さん、
長年にわたって「偉大な企業とは何か」をテーマに研究・執筆を続けておられます。
- 『ビジョナリー・カンパニー ― 時代を超える生存の原則』(原題:Built to Last, 1994)
→ 偉大な企業はどうやって生まれ、存続してきたか。 - 『ビジョナリー・カンパニー2 ― 飛躍の法則』(原題:Good to Great, 2001)
→ 偉大ではなかった企業がどうやって偉大な企業に「飛躍」できたか。 - 『ビジョナリー・カンパニー3 ― 衰退の五段階』(原題:How the Mighty Fall, 2009)
→ 偉大だった企業がなぜ、どうやって衰退していくのか。 - 『ビジョナリー・カンパニー4 ― 自分の意志で偉大になる』(原題:Great by Choice, 2011)
→ 予測不能な混乱の中でも偉大な成果を出す企業の特徴。
そして最新が、
- 『ビジョナリー・カンパニーZERO(ゼロ) ― 原点から成功をつかむ法』(原題:BE 2.0 (Beyond Entrepreneurship 2.0), 2020)
→ 企業の「原点」つまりスタートアップや小規模な組織の成長について。
(もともとはコリンズの初期著作『ビヨンド・アントレプレナーシップ』のアップデート版です。)
「なるほど、これを読めば4冊読んだことになるのでは?」と自分に暗示をかけ読み進めました。
本書籍は、組織を率いる立場にあるすべての人にとって、深く響く内容になっています。
とくに、現在マネージャーやリーダーとしてチームを導いている方には、自分のリーダーシップの在り方を見つめ直すヒントが数多く見つかるはずです。
今回は「正しい人を選び、責任を引き受け、ビジョンを描き、仲間を心から大切にすること」について学ぶことができました。
読書が苦手な学生さんや社会人の方、経営に関わる方にも、読みやすくコンパクトに要約しています。ビジネス書や自己啓発の本、まずは要点だけでも読んでみませんか。
『ビジョナリー・カンパニーZERO』
ゼロから事業を生み出し、偉大で永続的な企業になる
著者 : ジム・コリンズ、ビル・ラジアー
翻訳 : 土方 奈美
発売日: 2021年8月
出版社: 日経BP
ページ: 520ページ
【こんな人におすすめ】リーダーシップや組織づくりに悩むあなたへ

経営やマネジメントに悩んでいる人
チームがうまく機能しないと感じている方にとって、本書の「人材配置」や「ビジョンの共有」の考え方は大きなヒントになります。
特定のスキルよりも、価値観や文化へのフィットを重視する姿勢は、すぐに取り入れられる実践的な視点です。
リーダーシップを学びたい若手ビジネスパーソン
「リーダーとは何をすべきか?」という問いに、ただ命令することではなく、「社員の可能性を引き出すこと」が答えだと本書は教えてくれます。
人を率いる立場にある方には特に刺さる内容でしょう。
組織づくりを考える経営者・起業家
急成長するスタートアップにありがちな“人の質”の軽視。
本書では採用・育成の重要性が繰り返し語られています。創業期から文化を意識することの大切さを改めて実感できるはずです。
良い企業文化とは何かを考えたい人
「人を大切にする」とは何か。「社員に敬意を払う」ことがどれほど重要なのか。
本書では抽象的な価値観を、行動や仕組みに落とし込む具体例が豊富です。企業文化を変えたいと感じている方にも必読の一冊です。
成長を止めないキャリアを歩みたい人
他人ではなく「自分自身の成長」にフォーカスすることの大切さが、本書の根底に流れています。
日々の仕事のなかで、自分をアップデートし続けたい人にとって、前向きな刺激が得られます。
【10の学び】成功する企業が大切にしていること(ジム・コリンズ流)

人材こそが最大の資産|「誰を選ぶか」がすべてを決める
偉大な企業に共通しているのは、戦略以上に「正しい人材の選定」に力を入れていることです。
スキルよりも価値観への適合、組織文化との相性を重視し、不一致な人材は早期に交代させることが重要。
現実を考えると、そう簡単なことではありませんが、本書籍ではここが一番重要な点となっています。
ビジョンの共有が組織を動かす|目指すべき山を明確に
「どこに向かうのか」が曖昧な組織は、個人が力を発揮できません。
リーダーの仕事は行動で示すことであり、ビジョンを言葉で伝えるだけではだめ。理念と日常の意思決定が一致していることが重要です。
リーダーの責任は“導くこと”|肩書きよりも信頼
有能なリーダーは、社員に命令するのではなく、信頼によって行動を引き出します。
チームメンバーが「この人についていきたい」と思える存在であるかどうかが、組織力を大きく左右します。
組織文化を育てる|敬意・共感・対話の重要性
偉大な企業は、社内の誰もが尊重されていると感じる文化を持っています。
ポジティブなフィードバックを重ね、失敗を責めるのではなく学びに変える風土こそが、社員の主体性を育てます。
イノベーションは実行されてこそ意味がある|“行動”がすべて
斬新なアイデアがあっても、それを実行できなければ意味がありません。
本書では「クリエイティブな組織」は、行動する仕組みを持っていることが鍵であると語られています。
顧客と向き合う姿勢|“聞く”だけでなく“体験”する
顧客理解は、データやアンケートだけでは不十分。
現場に出て、実際に体験し、リアルな声に触れることが、新しい価値の創出につながります。
急成長には落とし穴がある|“人材”と“文化”が崩れる
拡大ばかりを追いかけると、採用の質や社員の満足度が犠牲になります。
本書は「成長スピード」と「マネジメント能力」のバランスの重要性を繰り返し説いています。
組織は“信念”でつながる|コアバリューの定着方法
企業の価値観は、ポスターに書いて終わりではありません。
日々の意思決定、評価制度、採用基準など、すべての行動に企業の価値観を反映させることで初めて浸透します。
「成果」よりも「成長」|失敗を恐れない文化
挑戦に失敗はつきもの。偉大な組織は、失敗を許容し、そこから学ぶ土壌を持っています。
「失敗=成長」という考え方が、次のイノベーションを生み出します。
偉大な企業に“完成形”はない|常に次の山へ
変化を恐れず、新しい目標(BHAG)を掲げ続けることが、企業のエネルギーになります。
本書では「立ち止まったら凍死するだけだ」という強烈なメッセージが印象的です。
【まとめ】ビジョナリーZERO|ビジョンと文化で組織は強くなる

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
あなたの組織にとっての「正しい人材」「共有すべきビジョン」とは何でしょうか。
偉大な組織をつくるのは、仕組みや戦略だけではありません。
正しい人を選び、責任を引き受け、ビジョンを描き、仲間を心から大切にする。
一つひとつの行動の積み重ねが、文化をつくり、未来をつくっていくことを改めて感じました。
そしてリーダーとは、特別な誰かではなく、日々、自分自身を見つめ直しながら、成長し続けようとする「姿勢」そのもの。
どれも当たり前のようでいて、実行するのは簡単ではないことばかり。
だからこそ、日々の行動や選択の積み重ねが、組織を偉大な方向へ導く鍵になるのだと気づかされます。
この記事を読んでくださったあなたが、どんな立場にあっても、何かひとつでも「これやってみようかな」と思えるヒントを見つけてくれていたら、うれしいです。
みなさんも「もっといいチーム、もっといい未来をつくる」を実践してみてはいかがでしょうか。
引用箇所において一部誤入力があるかもございません。予めご了承下さい。